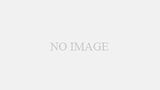私が普段診療している港区のサラリーマンとか経営者たちは
頭脳明晰だし感情もよくトレーニングされている
組織の中で生きるという事は
要するに我慢をするということなので
かなり社会的に高度な感情生活を送っている
そんな中でうつ病になったりパニック障害とか社交不安障害(昔でいう対人恐怖)、
強迫性障害とか睡眠リズム障害とか、ときには妄想性障害になったりもする
心療内科的な身体化障害も少なくない
全般に重症にならないのはやはり生活の基盤がしっかりしていて
家族がいて同僚がいて上司がいて
責任も役割もあるので
早期発見ができる体制になっているし
早期に治って欲しいと周囲が本気で思うからだと思う
そのような人たちが相手だと
薬を調整して
環境調整をしていれば
すっかり治ってしまうことが多い
これは地域の特性だと思う
大体の人が小学中学高校と秀才で通してきたような人たちだし
話を聞くとオール5とかの程度の人も少なくない
環境調整としては休職をすること、家族、同僚とのコミュニケーションを改善すること、
復帰してからあとの仕事の時間や内容を考えることなど
全く常識的なことで
精神世界的なマニアックな出来事もメカニズムも全く関係がないのだ
ただ、相手がオール5の人たちなので
こちらがあまりにアホだと見限られてしまう
そこが唯一難しいところだと思う
余計なことを言わないほうがどんどん自己発見して治ってゆく
最近は認知行動療法の本も多いし
対人関係療法の本などは大変読みやすいし実践しやすく出来ている
自分で認知の訂正ができるし
自分でコミュニケーションの訂正ができる
レコーディングもできるし
自己モニタリングも正確にできるようになる
本を読んでもできない人に我々が何かお話してできるようになることも難しいのではないかとも思う
そのように考えていくと
なかなか特殊な治療を港区を舞台にして行っているのだと思う
東大、慶応、ケンブリッジとかハーバードとかいろいろ
少しのヒントで悟るが多い
ヒントの出し方にコツがあるかもしれないとは思う
このレベルの人達は健康な睡眠と健康な食生活を再確立するだけで
みるみる良くなっていくものだ
そうでない人たちは病気が違うのだろう
特別なテクニックも特別な治療もいらないのだけれど
やはり人間として信用してもらえるかどうかがポイントになる
信用していない人から何のテクニックを学んでもあまり意味はないのではないかと思う
あの先生だったらこんなふうに考えるかもしれないなあ
くらいに内在化されればいいように思う
さて、そのような存在でいられるかどうか
日々なかなかきついことも確かである