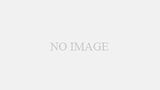インテークとかその後の面接で頭を整理しながらいくのには、「書式」をおおよそ決めて、それを埋めていく感じで聞くと、必要事項の漏れが少なくなりますね。ひとつの方法です。でも、クリニックとして全員を統一する必要はないです、いろいろあって良いと思います。
とっても極端な話、必要情報を全部埋めてくださいというのは、心理でなくてもできることですよね、精神科病院では違う職種の人がやっていたりする。
もっと別の観点で言うと、患者さんに質問票を渡してメールで返信してもらってそれをカルテに貼り付ければ済むことじゃないかとも考えられる。
心理の大切なポイントは聴く態度なんだと思う。情報として足りない部分はお医者さんの方で補いますし。どんな情報がとれたかではなくて、どのように出会って、どのように傾聴したか。そこをぜひお願いしたい。情報は後々埋めていけばいいわけだし。
学校で悪口言われて学校にいけなくなりましたとかの話を聴く場合、事実関係はおいおいでもいいので、やはりまず治療者と患者の間の信頼関係を築くことですよね。その際の態度全般。それが大事。
インテークに当たっては、最初は患者さんは話したいことがあるのだから、教えてくだい、それでどうなりましたか、その時はどんな気持ちでしたか、その時奥さんはどう話していたんですか、など、わりと大雑把に話を促す方向で聞いて20分くらい、それでいいと思いますね。
これはいろいろな流派もあると思うので一言では言えないんですが、私が報告を聞いていると、情報が少ないといわれるのが嫌なのか、不必要な細部を延々と語ったり、身振り手振りで擬音語を交ぜてとかの人もいて、カウンセラーの身振り手振りは必要ないです。短いほうがいい。三越でスイカを買った。でわかるところをなぜ、日本橋を渡って信号を直進し・・・・といわなくてはならないのか。情報が足りないと言われることがいやで防衛的になっているのではないかと思う。
簡単にポイントだけ教えてくださいというのは実はとつても難しいし危険だということはわかるけれどもトライしていこう。カルテはどうぞいくらも詳しく書いてください。
報告は5行くらいとか。そして、カルテが逐語みたいになって長くなったときには、5行程度のサマリーをつけておいて欲しい。
短く報告するというところで力量が問われるということなんでしょうね。でも、トライしていきましょう。
患者さんの前で、今の話をカウンセラーはこのように受け取りましたということを提示する。録音して再生するのではなく、カウンセラーが語る。これってかなり治療的だと思うんです。「あなたの今のお話は、わたしはこういうように受け取りました」というような説明はじつはあまりなされないですよね。話としてはその先のことで、お話はわかりました、ではこうしましょうとか、これはやめましょうとかの話になる。最近の積極的精神療法は特にそんな感じ。
でも理解、共感、傾聴を言葉でフィードバックする良い機会だと思うんです。
テープレコーダーとかビデオとかの機材も使える現代では患者さんの言葉をそのままで記録することの意義は昔ほど大きくないと思う。ローデータを残したいならビデオで良いし風景構成法とかの系統の物を残し、治験コーディネーターの使うチェックリストのような物を待合で書いてもらえばいいような気がする。
カウンセラーが書く記録は二人の人間の出会いの記録なんだと思う。
治療者が記録する物は特別な才能のある人をのぞいては客観的ではないだろう。これから20年後くらいに、あのころはこれが流行だったねえなんて言っているのだろうと思う。だからもうそれは前提でよい。
共感の言葉というのは患者さんの語りをまず先入観なく聴いて、治療者がそれを追体験するような具合になり、治療者の脳だったらどう反応するか、感じるかというところが共感ですよね。最初から肯定があるというものでもない。治療者の個人的な脳として受け入れられない場合はあるし『私、個人的にそれはだめだわ』というのも、体験を共有した上での誠実な話し合いでしょう。
でも、体験については追体験する形で共有しましたという感じになりたい。
話が拡散して申し訳ないけれど、体験を共有しましたと伝える言葉が大事だと思うので、共感はその先。体験をしっかり共有したとすれば、治療者の脳がそれなりに反応するはず。それは反感でも良いと思う。それもgenuineの要素だと思う。この点では肯定的とか共感という項目とgenuineという項目が矛盾する場合もあるのだろうと思う。
世間的な価値全般について判断中止して価値中立的にというのは理念としては考えられるが実際には難しいと思う。治療者の脳もその時代に生きている脳なので何が中立であるかを判断することは自分や自分たちではできないだろうと思う。
以下は後輩の人の文章です
ーーーーー
こちらが理解したことを患者様にお話するとぴたっときた時は、とても治療的で、満足感、信頼感につながるように思います。
違う場合、ややズレの場合も、お話して頂いて、こちらの理解につながり、修正していかれるので、やはりよいと思います。
患者さんの背後にぴったりくっついた視点になってみなさいといわれます。相対して中立的な視点を保持しているよりも、クライエント側に視点が移せている時のほうが、コミュニケーションが上手く行くと最近思うことが多いです
ーーーーーーー
私なりの細かいことを言えば、「患者さんの背後にぴったりくっついた視点」は大変良いと思います。しかし「相対して中立的な視点を保持しているよりも、クライエント側に視点が移せている時」のところはぴったり来ません。
ゲゲゲの鬼太郎のおやじみたいに鬼太郎の体験の一部始終を知る、追体験するのは根本的に必要。
このことを「クライエント側に視点が移せている」と言っているのだと思います。
「相対して中立的な視点を保持している」というのは何のことなんだろう。学校の職員であれば学校の秩序を守るとか、会社の内部であれば会社の利益に配慮するとか、そのあたりを考慮して「中立」「クライエント側」とかの区別を考えるのかもしれません。我々のよう
な外来面接の場合には問題なくクライエント側の立場で追体験できると思います。
カウンセラー2011-06-10
 未分類
未分類